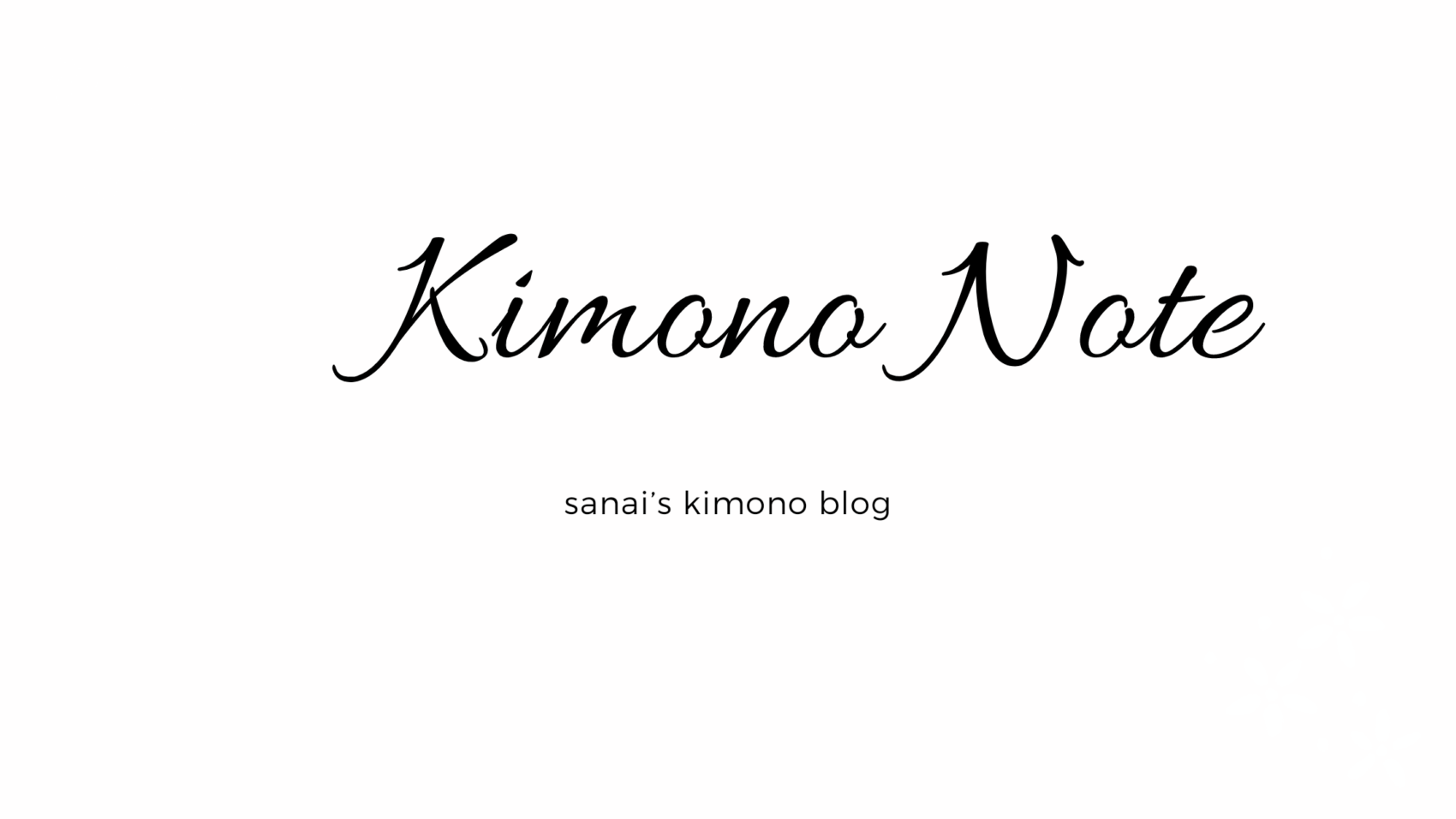着物を着るにあたって必要な着付け小物や和装小物。たくさんの種類があるので、何が必要なのか、またどれを選べばいいのか迷ってしまうことも。そんな初心者さんのために、最低限そろえておいた方がいい和装小物についてご紹介。帯揚げや帯締め、足袋といった基本的なアイテムをチェックしておきましょう!
※本ページにはプロモーションが含まれています
▼▼着付け小物についてはこちらをチェック▼▼
『着付け小物って何が必要なの?』
基本的な和装小物の種類
帯揚げ(おびあげ)

帯揚げは、袋帯や名古屋帯のお太鼓結びに欠かせないアイテム。帯枕を隠す役割があるほか、帯から少し見えるためコーディネートのアクセントにもなります。半幅帯や兵児帯びを結ぶ場合はなくてもOKです。
素材は正絹の綸子(りんず)や縮緬(ちりめん)が一般的ですが、夏は主に絽(ろ)や紗(しゃ)が使われます。無地だけでなく、絞りや刺繍、ぼかし染めなど施される技法もさまざま。最近では色柄の種類が豊富なポリエステルなど化繊(化学繊維)や木綿レースの帯揚げなども多く見られます。
<主な素材の特徴>
| 縮緬 | 小さな凹凸状のシボがあって結びやすいため初心者におすすめ。シワになりにくいというメリットもあります。ふっくら温かみのある印象で、主にカジュアル向け。 |
| 綸子 | なめらかで光沢感のある素材。 ややシワが寄りやすいのが難点ですが、上品な雰囲気を演出できます。 |
| 絞り | ボリューム感があり、華やかさが求められる振袖などによく使われます。 ふっくらとしていて、やや若々しい印象に。 |
帯締め(おびじめ)

帯結びを固定するための補助具的な役割を持つ帯締め。帯揚げ同様、特にお太鼓結びのマストアイテムです。半幅帯や兵児帯を結ぶときは使わなくてもOKですが、コーディネートのアクセントになるため、飾りとして取り入れている人も多く見られます。
帯締めの種類や色柄によって格が異なるので、合わせる着物やつけていくシーンによって選んでみましょう。
帯留め(おびどめ)

主に三分紐と呼ばれる細くて薄手に帯締めに通して楽しむ帯飾り。
季節やシーンによって使い分けたり、帯や着物とのバランスを考えたりして、コーディネートにアクセントを与えることができます。基本的にはカジュアルシーンで楽しむものですが、真珠や珊瑚などの素材のものであればフォーマルシーンでも使えます。
足袋(たび)

浴衣の場合は足袋不要ですが、着物の場合は必ず履きます。最初に買うなら、フォーマルからカジュアルまで使える白足袋がおすすめです。
足袋の歴史
元々足袋はほとんどが革製で、指先も割れていない形でした。
室町時代以降に現在の形になりますが、この頃はまだこはぜが付いておらず、紐で結ぶものだったのだそう。
こはぜが付いたのは、江戸時代の元禄年間頃と言われています。
足袋の色柄
・白足袋
フォーマルからカジュアルまで使える定番の足袋。
・色足袋 / 柄足袋
色や柄が入っている足袋は、カジュアル用。フォーマルでは着用しません。
コーディネートのアクセントになり、また汚れが気にならないのもメリットです。
他にも、汚れ防止や保温を目的とした、足袋の上に履く足袋カバーと呼ばれるものもあります。
足袋の素材
足袋の素材は主に綿(キャラコ)。
通気性や保温性に優れているので、年中使うことができます。
夏用として麻やレース素材のものも。
冬用にもネルや別珍もありますが、これはカジュアル向けになります。
他にも最近では伸縮性のあるストレッチタイプのものも多く、基本的にはカジュアルシーンで使うものになりますが、ものによってはフォーマルでもOK。
長時間正座をするときなどは、足首の締め付けが少ないストレッチタイプのものがおすすめです。
足袋のサイズ
サイズは実際メーカーによってまちまち。
一般的には足のサイズより5mm小さい足袋を選ぶのが目安になります。
ただし、長く正座するときは締め付け感の少ないワンサイズ大きめのものが◎。
好みの履き心地やシーンによって選ぶのもいいでしょう。
こはぜとは?

足首の部分についている金具のことをこはぜと呼びます。
こはぜの枚数は一般的には4~5枚。
この枚数は、TPOによって厳密な決まりがあるわけではありませんが、使うシーンや地域によって好まれる枚数は多少異なります。
例えば、関東では少し素足が見える方が粋だとされているため4枚が主流ですが、関西では素肌を見せない奥ゆかしさを尊重し、5枚が好まれるのだそう。
さらに、結婚式の場合慶事に「4」という数字は不釣り合いということで5枚のものを使うのがほとんどです。
日本舞踊など踊りの場合は、足元の安定感を得るために5~6枚のものが多用されます。
ちなみに、踊りで使う地下足袋の中には、なんとこはぜが12枚もついているものも。
こはぜは1枚違うだけで約1.5cmも深くなり足のフィット感も違ってくるので、シーンで使い分けるのはもちろん、履き心地で選んでもいいでしょう。
履物

着物にあわせる履物といえば、草履や下駄。草履は台の高さや色にもよりますが、フォーマルからカジュアルまでOK。下駄はカジュアル向けのものになります。
より個性的なオシャレを楽しみたいなら、ブーツやパンプスなど靴をあわせてモダンに楽しむのもおすすめです。
バッグ
着物専用のバッグも売られていますが、シーンによっては和洋兼用でも構いません。
フォーマルシーンの場合は、ラッチバッグやビーズバッグなど上品なものを選ぶのが一般的。留袖や振袖など礼装の場合は、草履とセットになったフォーマル用のバッグがおすすめです。
便利な小物の宝庫★おすすめのネットショップ
もっとアイテムをチェックしたいという方は、着物好き御用達の雑誌『七緒』の公式オンラインショップこまものや七緒
![]() がおすすめ!
がおすすめ!
着物や帯、和装小物のほか、あったら便利なアイテムが目白押しなので、ぜひ覗いてみてください♪
コーディネートをより華やかに彩ってくれる和装小物。
着物や帯だけでなく、帯締めや帯揚げなどの小物もたくさんそろえておくと、シーンや季節に応じた多彩な装いを楽しむことができます。コーディネートの脱マンネリのヒントにもなるので、ぜひ小物のオシャレも極めてみてください♪