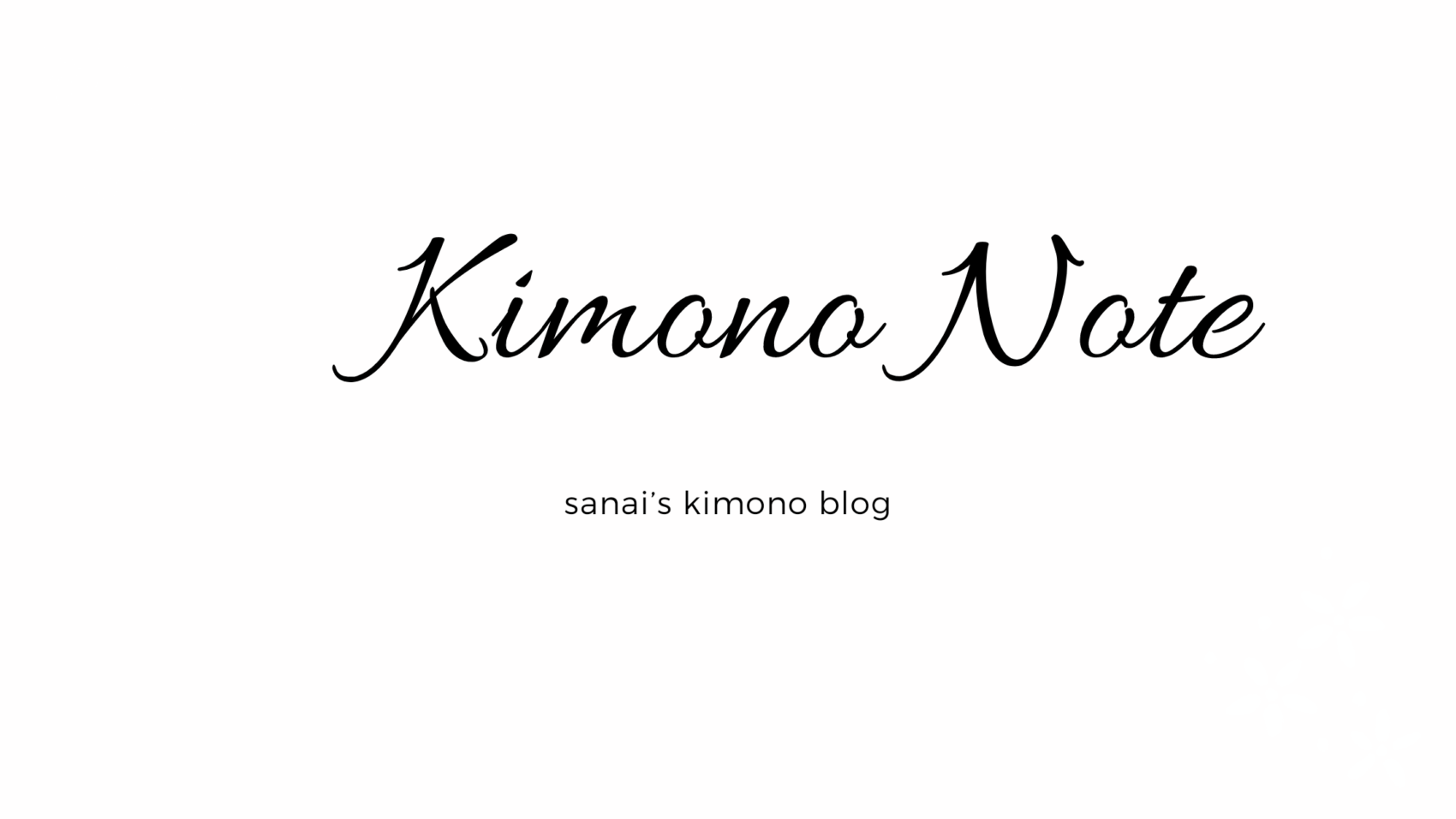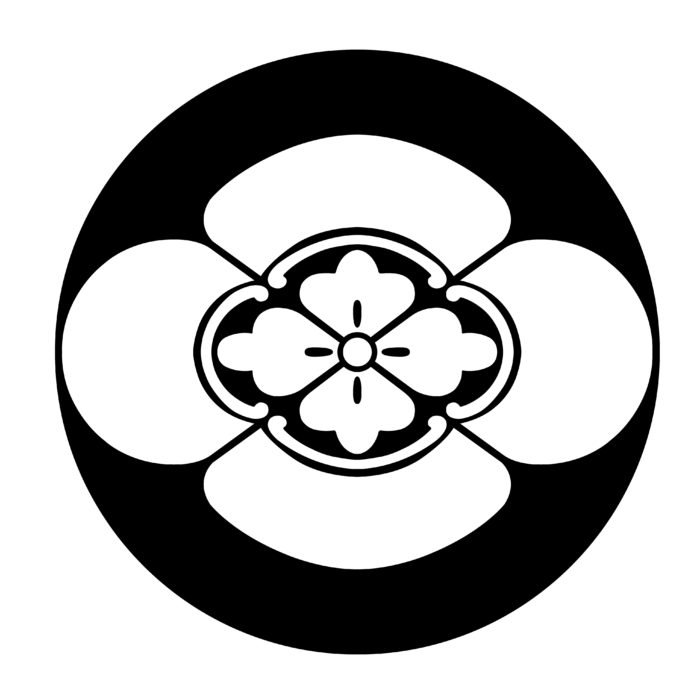今では卒業式に着るのが一般的な袴。けれども、最近では袴の色柄のバリエーションも増え、お洒落着として着用する人も増えてきています。
着付け動画も紹介するので、早速着付けを練習して卒業式などフォーマルの場ではもちろん、カジュアル着物としても楽しんでみてはいかが?
※本ページにはプロモーションが含まれています
卒業式に袴を着用する理由とは?女性袴の歴史
袴自体の歴史は古く、その原型は古墳時代には存在したと言われています。元々男性用として着用されていましたが、平安時代になると一定の身分以上の女性も袴を身につけるようになります。
しかし、鎌倉時代以降女性が袴を履く習慣は衰退。宮中の女官を除いては、袴は男性の着物として長く扱われることとなります。

現在の女性用の袴、いわゆる女袴が登場したのは、明治時代のこと。
当時、西欧文化の流入により、椅子に座るライフスタイルが公式の場にも浸透。さらに女子教育、及び女性の社会進出が進むとともに、女性の着物にも動きやすさが求められるようになりました。当初は女性も男性用の袴を着用していましたが、淑やかでエレガントな女性像が求められていた当時、その荒々しいスタイルは世間から奇異の目で見られ、新聞紙上には投書による批判が相次いだといいます。今でいういわゆる“SNS上で炎上する”のような状態だったのでしょう。
最終的に、政府によって明治16年に女性の男袴の着用が禁止されました。

その後、女学校の普及とともに女袴が誕生。経緯には諸説あるようですが、跡見女学校を開いた跡見花蹊(あとみ かけい)が考案したと言われています。素材は動きやすいようにウールのメリンスを採用し、色は紫と決められていました。色が紫だった理由としては、花蹊が袴について昭憲皇太后にお伺いを立てた際、「宮中女官と同じ緋の袴仕立てで紫を用いたらよかろう」というお言葉を賜ったからだそうです。
女袴は、男性用とは異なり、スカートのような行灯(あんどん)型で背中に腰板がついていないものだったため、女性らしい優美な着姿を表現できる新しいスタイルでした。

その後、下田歌子が創立した実践女子学園から、海老茶袴が登場。高貴な色であった紫を一般で使うのは恐れ多かったのか、紫がかった暗赤色である海老茶色が女学生の袴の定番に。
明治32年頃には海老茶袴に銘仙の着物、革靴、そして庇髪に大きなリボンをつけた女学生スタイルが大流行。紫式部になぞらえて海老茶式部と呼ばれ、若い女性たちの注目を集めました。
銘仙の着物とは?>>
明治から大正にかけてトレンドとなったこの女学生スタイルも、洋装文化が広がるとともに見られなくなりましたが、当時の名残が卒業式での礼装として定着し、現在まで受け継がれています。
参考:『あのときの流行と「美しいキモノ」』富澤輝実子
袴を着る時に必要なアイテム
袴を着る時は、一般的に以下のものが必要になります。
着物・袴・半幅帯

卒業式用の袴は、着物や帯とセットで販売・レンタルされていることがほとんど。
卒業式の着物は、二尺袖の着物を合わせるのが一般的です。二尺袖とは袖丈が約76cmのもの。振袖よりも袖丈が短くて動きやすい上、一般的な着物よりは長いので程よく華やかさも出せます。
着物を着た後は半幅帯を締め、その上から袴を履きます。半幅帯はほとんど見えませんが、袴と着物の間からちらっと見えるため、コーディネートのアクセントになります。
長襦袢・肌襦袢・裾除け
着物の下には長襦袢を、さらにその下には肌襦袢・裾除けを着ます。二尺袖の着物を着る場合は、袖丈にあわせて長襦袢も二尺袖用のものを選ぶとよいでしょう。
肌襦袢と裾除けは、一体化しているワンピースタイプのものもあります。
半衿
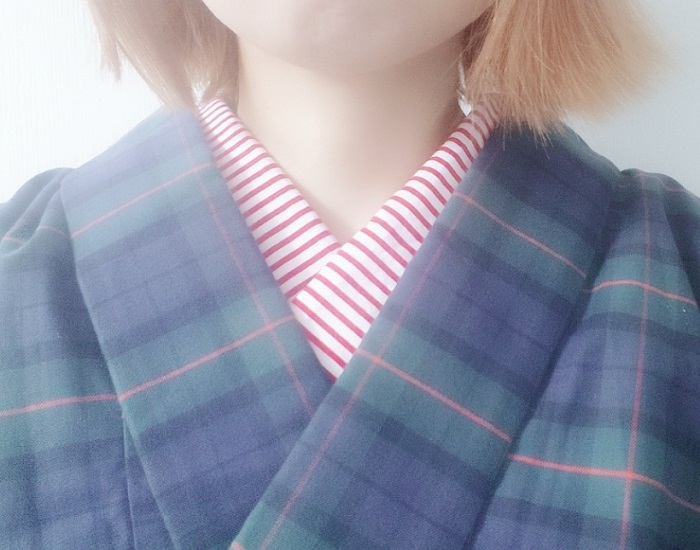
半衿は、長襦袢の衿に縫い付けるもの。着物の衿元から少し覗くだけですが、色柄によって雰囲気がガラリと変化。卒業式などハレの日に着る場合は刺繍などが施された豪華なものを選ぶと、顔周りが華やかな印象になります。
着付け小物
袴を着用する際は、腰紐、伊達締め、コーリンベルト、帯板、衿芯といった着付け小物が必要です。着付けの仕方によって多少使うアイテムが異なるため、お店などで着付けをしてもらう際は必要なものを確認しておくとよいでしょう。
着付け小物をまったく持っていない場合は、一つずつ買うよりセットで買ったほうがお得です。
また、体型によっては補正したほうが着姿を美しく見せられたり着崩れを防いだりできるため、タオルやガーゼも用意しておきましょう。
足袋・履物

履物は、クラシカルに見せたいときは草履を、モダンな印象にしたいときはブーツを合わせるのがおすすめです。
草履の場合は足袋が必須。卒業式のようなフォーマルな場で着用する場合は白足袋が基本で、ソックスタイプではなくこはぜのついたタイプのものを選んだ方がよいでしょう。
普段着としてカジュアルに袴を履くメリット

袴というと卒業式などフォーマルのイメージが強いですが、最近は普段着としてオシャレにコーディネートできる色柄のものが多く登場しています。そのため、カジュアルシーンで普段着として楽しむのもおすすめ。
コーディネートの幅が広がるのはもちろんですが、普段着の袴には次のようなメリットもあります。
雨の日に着物の裾が濡れるのを防げる
袴は、雨の日に着物の裾が濡れてしまうのを防いでくれるメリットがあります。ただし、正絹の袴は水に弱いため、ポリエステルなど雨に強い素材のものを選ぶとよいでしょう。
また、着物の裾がはだけやすい風の強い日にもおすすめです。
着丈の短い着物でも気にならない
リサイクルやアンティークの着物など、着丈が短くて普通に着付けるのが難しい着物も、袴と組み合わせれば上手く丈をカモフラージュしながらオシャレに着こなせます。

着物より歩きやすい
袴の歴史でご紹介した通り、もともと女性が袴を履くようになったのは着物よりも歩きやすいから。裾がはだけたり、足で着物の裾を踏んでしまったりする心配がないので、着物でたくさん歩く日や自転車に乗りたいときなどにもぴったりです。
礼装としてはもちろん、和装をより活動的に楽しむことができる優秀アイテムにもなる袴。コーディネートや着物で出かける場所の選択肢をさらに広げたい方は、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか?