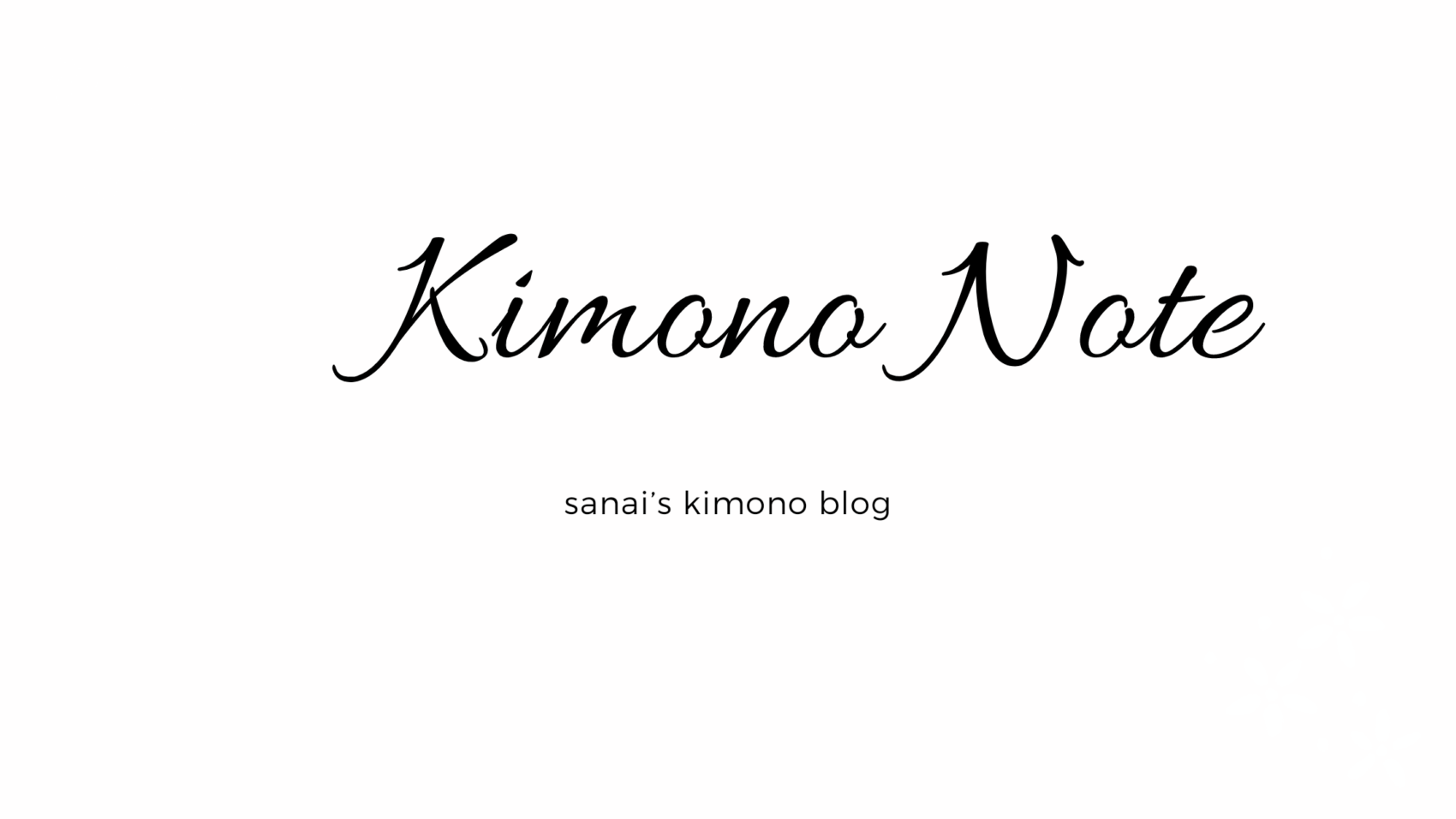カジュアルシーンでの代表的な着物として知られている、小紋(こもん)。
そもそも小紋とはどのような着物のことを指すのでしょうか。また、似たものに江戸小紋もありますが、その違いとは一体何なのでしょうか?
今回は、そんな小紋の基本について解説します!
※本ページにはプロモーションが含まれています
小紋の特長とは
素材は絹が一般的

小紋の素材は絹が基本。最近ではポリエステルなど化繊のものもありますが、小紋ではなく化繊の着物として分類されることもあります。
紬や木綿の着物もカジュアル着物として知られていますが、小紋とは全く別物。小紋と紬&木綿の着物の大きな違いの一つが染めるタイミングです。
小紋は生糸をそのまま白い状態で織って、反物にしてから絵柄を施していく後染めの着物。一方で紬や木綿は、先に糸を染めてから、織りによって柄を出していく先染めの着物です。着物は後染めの着物の方が格が高いとされるため、紬や木綿より小紋の方が一般的に格上になります。
同じ柄が繰り返されたデザイン

小紋と同様、絹で作られている留袖や振袖、訪問着といったフォーマル着物との違いはどこにあるのでしょうか?
ポイントになるのが、デザインです。
小紋は、同じ柄が繰り返し描かれているのが一般的。縞模様やチェック柄など全体的に柄がある総柄と、小さな柄が散らばって描かれている飛び柄があります。
一方で留袖や振袖、訪問着は、一枚の絵画のように繋がった絵柄になっており、礼装にふさわしい華やかな雰囲気が特長です。
小紋はどこに着ていけるの?

フォーマルシーン以外であれば基本的に着用可能。ホテルでの食事やアフタヌーンティー、観劇、美術館、友達との気軽な食事会などで着ることができます。
クラシカルで上品な雰囲気のものからカジュアル感が強いモダンなものまで、色柄のバリエーションが多いのも魅力。好みや着ていく場所によってぴったりのものを選んでみましょう!
江戸小紋との違いとは?

小紋の中でもっとも格が高いものとされているのが江戸小紋。最大の特長は何といってもその繊細な柄です。細かい柄が連続しており、遠くから見ると無地に見えるほど。最近ではプリントものも多いですが、職人による手描きの方が、柔らかく上品なニュアンスを感じられます。
また、江戸小紋の柄は武士の裃を由来としていることもあり、紋を入れればセミフォーマルでも着用可能。色無地感覚で着ることができます。
色無地とは?>>
シンプルなデザインなので、合わせる帯や小物によって格や印象がガラリと変化。幅広いシーンで活躍してくれる上に初心者でも帯合わせがしやすいので、1枚持っておくと便利な着物です。
***********
色柄豊富な小紋は、普段着として多彩な個性を発揮できる着物。ぜひあなたも小紋で着物ファッションを楽しんでみてはいかがでしょうか?