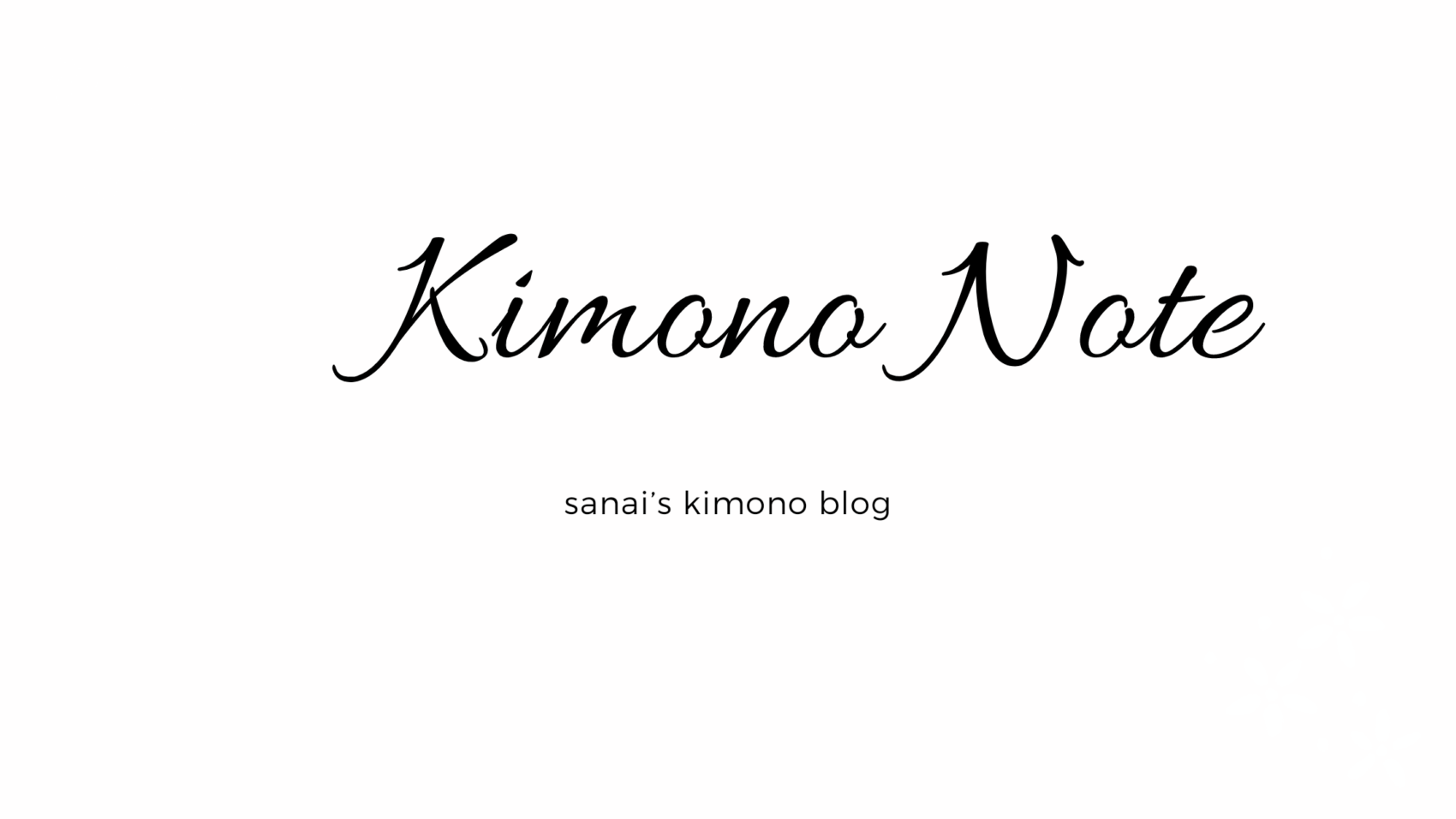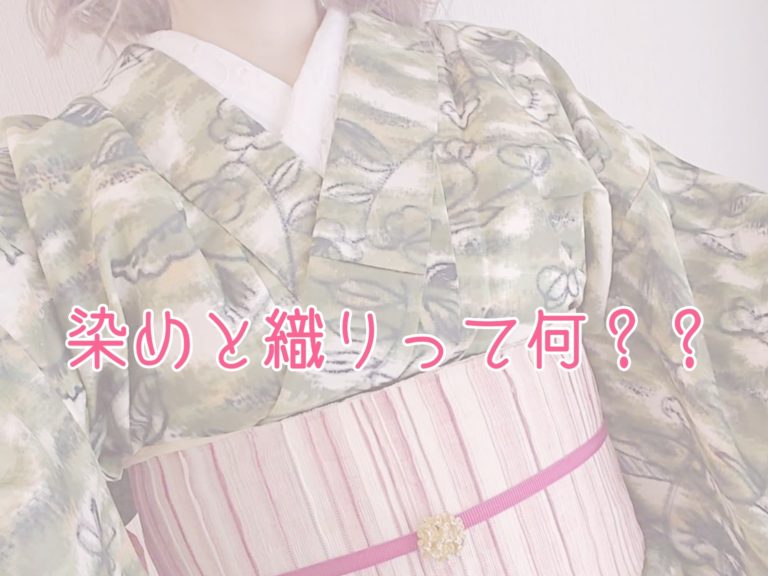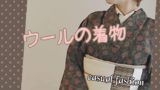着物というと「絹」のイメージが強いかもしれませんが、実はその素材はさまざま。木綿や麻、ポリエステルなどたくさんの種類があり、シーンや季節によって使い分けられます。
また、染めや織りといった技法によっても格や風合いが異なるので、一見難しく感じる反面、多様なコーディネートを楽しめるという魅力もあります。
今回は、そんな着物の生地の種類と染め・織りの違いをご紹介します!
主な着物の素材
絹(きぬ)

着物の代表的な素材。とろみがあって柔らかい着心地が快適です。
| メリット | 保湿性や吸湿性に優れていて、夏は涼しくて冬は暖か。肌触りも滑らかで、裾捌きも抜群。 |
| デメリット | 水や摩擦、日光に弱く、シミになりやすい。 |
| 仕立て | 袷(10月~翌5月)、単衣(5~6月、9~10月)、夏生地の単衣(7~8月) |
| 着用シーン | フォーマル~カジュアル |
| お手入れ | 着物クリーニング店へ依頼 |
ポリエステル

絹より値段がお手頃で、かつお手入れしやすい素材なので、初心者さんにもおすすめ。
| メリット | 自宅で洗濯できるのでお手入れが楽。また、汗や太陽の光、摩擦などにも強く、虫もつきにくい |
| デメリット | 通気性や肌触りが絹には多少劣る。また、火や熱に弱いので、アイロンがけには注意。静電気が起きやすい。 |
| 仕立て | 袷(10月~翌5月)、単衣(5~6月、9~10月)、夏生地の単衣(7~8月) |
| 着用シーン | フォーマル~カジュアル |
| お手入れ | 自宅で洗濯可 |
ウール

絹やポリエステルに比べると、ハリのある着心地。普通のウールの他、シルクウールやサマーウールなどもあります。
| メリット | 皺になりにくく、保湿性や保温性が高いので着心地は暖か。 |
| デメリット | 虫が付きやすいので、保管には防虫剤が必須。 |
| 仕立て | 単衣仕立て(9月~翌年6月) |
| 着用シーン | カジュアル |
| お手入れ | 自宅で洗濯可能。ただし縮む場合があるので注意。 |
ウールの着物については↓↓の記事でさらに詳しく紹介しています。
麻(あさ)
夏着物の代表的な素材で、ナチュラルな風合いが魅力的。江戸時代においては、木綿が一般的になるまでは、庶民は季節問わず麻を着用していたようです。
| メリット | 通気性に優れているため、夏でも涼し気。汗をかいてもすぐに乾きやすい。 |
| デメリット | 膝の裏部分などに皺が付きやすい。ハリがある生地なので、チクチクすることも。 |
| 仕立て | 夏単衣仕立て(7月~8月) |
| 着用シーン | カジュアル |
| お手入れ | 洗濯可能。ただし毛羽立つ場合もあるので、着物専門クリーニングがおすすめ。 |
木綿

軽くて柔らかい肌触りが特徴で、浴衣としてもよく使われる素材です。デニム着物も木綿着物の一種です。
| メリット | 吸湿性・通気性に富んでいる上、熱にも強いのでアイロンがけOK。 |
| デメリット | シワになりやすい |
| 仕立て | 単衣仕立て(9月~翌年6月) |
| 着用シーン | カジュアル |
| お手入れ | 洗濯可能。ただし、縮むことがあるので注意。 |
木綿の着物については↓↓の記事で詳しく紹介しています!
「染め」と「織り」の違いについて
着物には、後染めの「染め」と先染めの「織り」の着物があります。
染めと織りでは雰囲気が大きく異なり、格も違ってきます。
染めと織りの位置づけ
染めの着物 > 織りの着物
織りの帯 > 染めの帯
一般的に着物においては染めが格上、帯においては織りが格上。
例えばフォーマル着物の代表・振袖の場合、着物は染め、帯は織りになっています。
ただし、カジュアルな染めの着物やセミフォーマルでもOKな織りの着物もあるので、技法や柄行、シーンによって使い分けが必要です。
染めの着物や帯とは?

染めとは、その名の通り染めを施した織物のこと。白糸(主に生糸)を、真っ白のまま織って白生地の反物を作ります。
そしてその白生地に絵柄を染めていきます。染め方は手描きや型染など色々ありますが、鮮やかな色彩やバリエーション豊かな柄を楽しむことができます。
織りの着物や帯とは?

織りは、染めとは違って織ることによって柄を出した織物のこと。白糸(主に紬糸)を最初に染めて、その染まった糸で織って反物を仕上げます。
染めとは違って素朴な風合いが魅力的。礼装の帯の場合は、重厚感があって華やかな印象になります。
【保存版】袋帯から名古屋帯、半幅帯まで!帯の種類を全部見せ★>>
******************
TPOや自分の好みに合わせて、色柄だけでなくその素材のよさも感じながらぜひ着物を楽しんでみてください♪