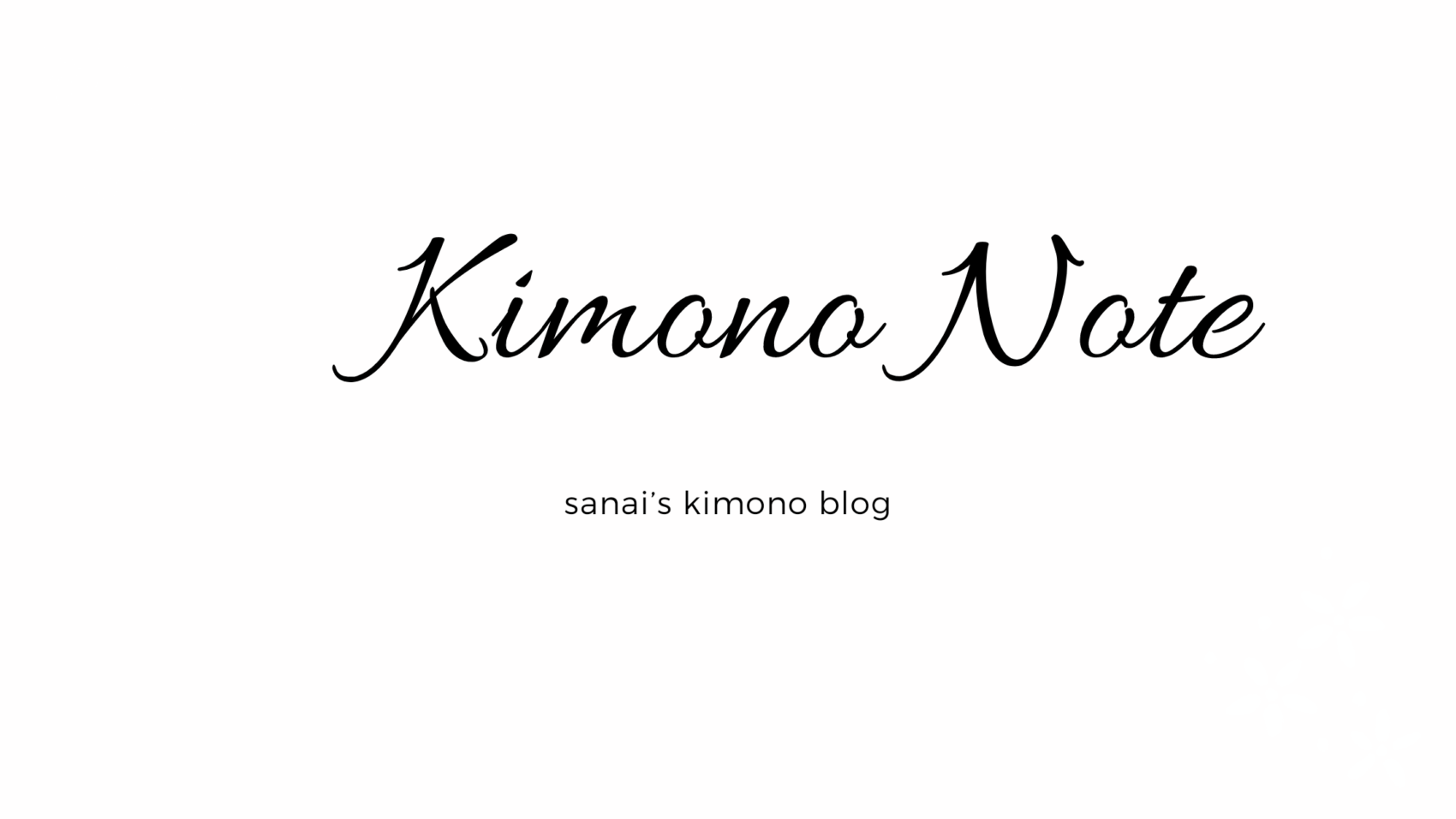紅型(びんがた)とは、専用の型を使って染めていく技法・型染の一種で、礼装から普段着まで幅広く使われています。
今回は、そんな紅型を代表する琉球紅型についてご紹介します。
※本ページにはプロモーションが含まれています
琉球紅型の歴史

沖縄の紅型の誕生は琉球王朝時代。
中国や朝鮮、日本、東南アジアなど諸外国との交易が盛んにおこなわれており、各地の染織技術の影響を受けて誕生したものと言われています。紅型で染められた着物は、もともとは王家とごく少数の家臣のみが着用できる特権階級の象徴のようなものであり、現在のように誰もが着れるものではありませんでした。
今でこそ多くの方に愛され着用されている紅型ですが、当時は権力の象徴として一部の特権階級にしか着用が許されておらず、尚王家の日常着や、国賓向けの礼装、行事の際の晴れ着、国賓を歓待する芸能の舞台衣装として用いられていました。
さんち大辞典『紅型』

王家お抱えの職人は首府であった首里に居住。手厚く保護されていましたが、中でも城間家、知念家、沢岻家は紅型三宗家として重用されていました。
しかし、その様相が一変したのが1879年の明治政府による廃藩置県でした。いわゆる琉球処分によって日本の県として統合されることになり、450年続いた琉球王国は滅亡したのです。それに伴って職人たちも仕事を追われることになり、紅型は衰退に向かいます。
さらに、第二次世界大戦によって多くの紅型の道具も焼失してしまいますが、戦後紅型三宗家の城間栄喜氏や知念績弘氏らが再興に尽力し、沖縄の伝統染織品として今なお守り続けられています。
琉球紅型の特徴

琉球紅型は、南国らしい鮮明な色合いと大胆な柄行が特長です。沖縄にはたくさんの染め織物がありますが、その中でも紅型は唯一の後染め。型紙を使った型染と円錐状の糊袋で描く筒引きの2種類があり、それぞれ顔料や染料で彩色されます。
中国や日本をはじめとする周辺地域の影響を受けた古典的な要素を持ちつつ、沖縄の自然や風物など独自のものも取り入れた柄で、独特の雰囲気を醸し出しています。
紅型の他に、藍型(えーがた)と呼ばれる型染めがあります。これは、藍一色で染めたもの。この藍型に対して多色染めのものを紅型と呼んでいます。

制作工程
染料は天然染料を使用。紅型の型に糊を置き、その間に色を挿していきます。今回は、沖縄の金城紅型染工房さんの動画を拝借させていただきました。
①型彫り
▼▼工程の続きはこちら▼▼
『金城紅型染工房』公式サイトへ
江戸紅型と京紅型との違いとは?
沖縄だけでなく、本土でも紅型の染め織物は生産されています。その主なものが江戸紅型と京紅型。
これらは元禄時代に近隣諸国との交易によって、琉球から京都や江戸にその技法が伝えられたといわれています。
渋さが粋な江戸紅型
東京で作られている江戸紅型。琉球紅型が植物の染料を使うのに対し、江戸紅型は顔料を使うため、ふんわりとした優しい色味になります。
制作手法も基本的には琉球紅型と同じですが、染め一色に対して1枚の型紙を用いるので、柄によっては数百枚の型紙を使うこともあるのだそうです。
同じく江戸を代表する型染・江戸小紋についてはこちら>>
はんなりとした風合いで魅せる京紅型
京都で作られる京紅型。多くは、京友禅の顔料を使って染められます。基本的にはゴム糊で型糸目を置く型友禅の手法がとられています。模様の色挿しは琉球紅型と同じく、刷り込みで行われているものもあるのだそうです。
友禅とは?>>
もともとは、琉球紅型、江戸紅型、京紅型はそれぞれその土地の雰囲気を反映したデザインが特長でしたが、最近ではデザインの多様化が進み、違いがわかりにくいものも多くあります。
それぞれの固有の雰囲気を感じつつも、厳密に線引きせず紅型ならではの美しさを楽しんでみるのも良いでしょう。