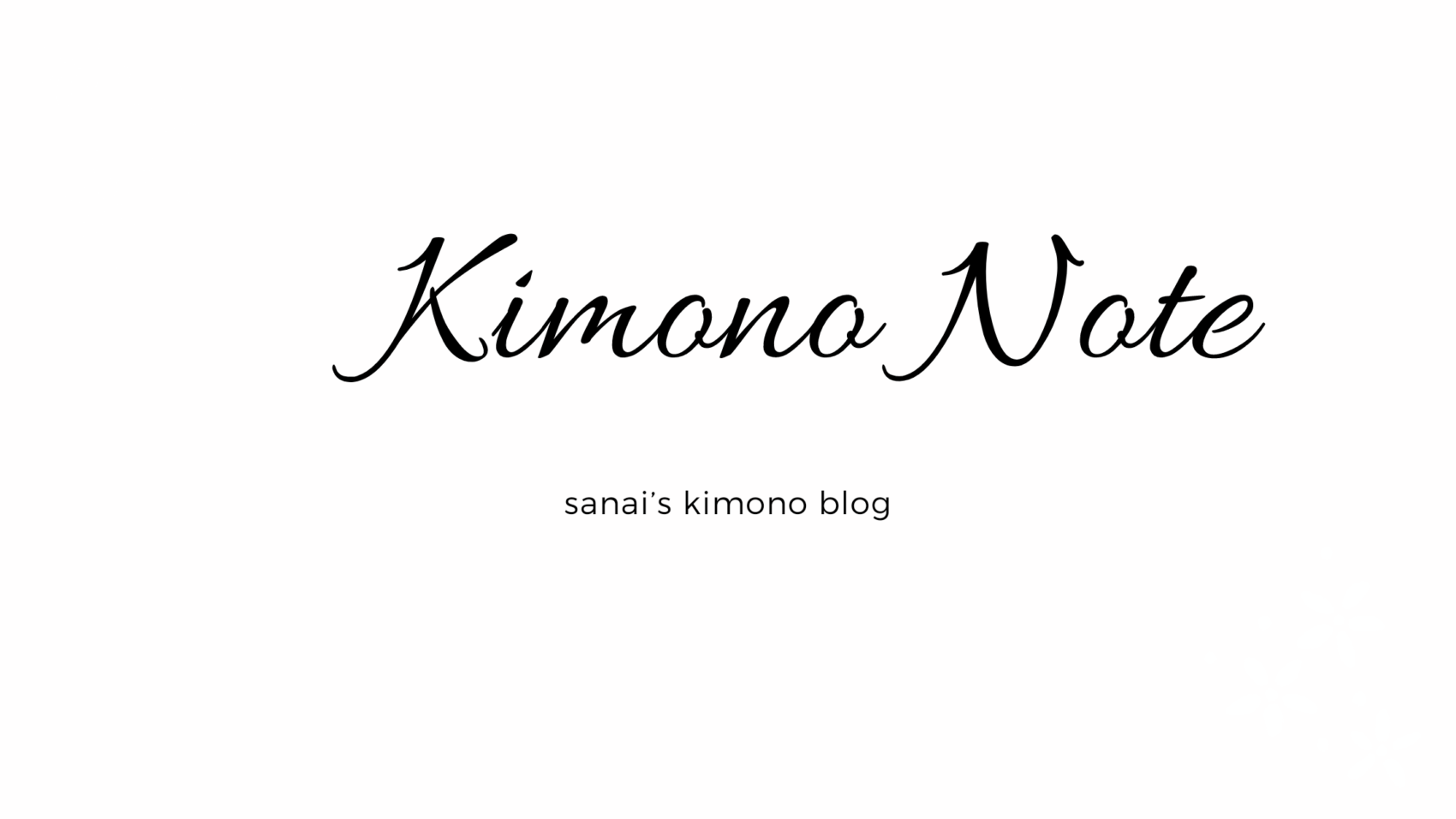今回は、着物を着た後の小物のお手入れ方法をご紹介!
「帯揚げや帯締め、足袋などは洗濯できる?」
「汚れたときはどうすればいい?」
など、お手入れのイロハをチェックして、大切な小物をキレイな状態で長持ちさせましょう♪
※自己責任になる部分もあるので、もし失敗するのが不安という方は着物専門クリーニング業者に依頼することをおすすめします。
※本ページにはプロモーションが含まれています
【半衿】素材によって扱いに注意して

頻繁に着る人は、毎回洗わなくてもOK。
長期間着ない時や数回着用した後、また汚れが気になった時に洗濯する程度で問題ありません。

ポリエステルや木綿など、洗える半衿は、ネットに入れて洗濯機で洗ってOK。シワの原因になるので脱水はせずに、手で絞って日陰干ししましょう。
正絹や縮緬、レース素材、刺繍入りなどは、セルフで洗わない方が無難。色落ちや生地の縮みなどの可能性があるため、着物専門のクリーニング業者への依頼をおすすめします。
【帯締め】使った直後は陰干しを

帯締めは、基本的に洗濯不要です。
解いた直後は湿気を含んでいるため、半日ほど陰干ししておくだけでOK。
もし汚れが気になるときは、ベンジンをたっぷり入れた容器やビニール袋などに帯締めを浸してシャカシャカとシェイク♪
そのあとタオルなどで水分を拭きとって陰干しします。
まず帯締をビンに入れ、ドボドボッと帯締が浸るくらいにベンジンを入れます。そしてシャカシャカシャカ!としばらくシェイクして、取り出します。このとき、房の部分はギュっと絞ります。素手だとちょっと爪が白くなったので、絞るときには、炊事用の手袋などをするとよいと思います。
房を整えて陰干しすると、ベンジンが揮発して気持ちよい程早く乾きます。
出典:いち利モール
ちなみに、ベンジンは引火性のものなので火の気のない場所で、かつ換気をしっかりした状態で行います。肌が弱い人は手袋をした方が良いかもしれません。
また、房の部分が毛羽立っているときは、アイロンややかんなどの蒸気を当てるとまとまりやすくなります。
使用しない時は房カバーをつけておくと、キレイな状態で保管できますよ♪
【帯揚げ】帯締め同様ベンジンで洗える!

帯揚げも基本的に洗濯は不要で、使った後は半日ほど陰干しにして湿気を飛ばしておけば大丈夫です。
汚れやくすみなどが気になるときは、帯締め同様ベンジンでの洗濯も可能。
ベンジンが入った容器やビニール袋などに帯揚げを浸してシャカシャカ振った後、やさしく絞りながら取り出し、残った水分はタオルなどに吸わせて陰干しします。
ポリエステルや木綿素材の帯揚げであれば、洗濯機で洗ってしまってもOKです。
シワが気になる時は、当て布をして低温に設定したアイロンをかけます。
(※素材によってはアイロンNGもあるのでご注意を!)
金糸が入っている場合は、その部分は避けるようにしましょう。

また、洗濯洗剤を使った洗い方をすなおさんが紹介されていたので、こちらもぜひ参考にしてみてください!
【足袋】脱いだ後はなるべく早めに洗濯を

足袋は汚れやすいため、脱いだらその日のうちに洗濯するのがおすすめ。
汚れがひどい時は、中性洗剤をつけた歯ブラシでこすったり、脱いですぐに水に浸けて一晩おいたりしてから洗濯すると、キレイに落ちやすくなります。
ちなみに綿100%の足袋の場合は縮みやすくなるため、洗濯後はしっかり生地を伸ばして干すと良いでしょう。
汚れ防止のために、出かける時はあらかじめ足袋カバーをしておくのもアリです。
【肌襦袢・裾除け】ネットに入れて洗濯機へ!
肌襦袢や裾除けは、洋服の肌着同様綿やポリエステル素材のものがほとんどなので、たたんでネットに入れて洗濯します。
シワが気になる部分は、アイロンをかけてもOKです。
【草履・下駄】湿気を飛ばしてから収納

脱いだ後、すぐに箱にしまうのはNG。湿気を飛ばすため、風通しのいい場所に一晩くらい立てかけておくとよいでしょう。
台は濡らした布でサッと拭いておきます。保管するときは、鼻緒キーパーを使うと鼻緒の形をよりキレイな状態でキープできます。
ちなみに、保管するときに新聞紙やビニール袋に入れないようご注意を。時間が経つと、色移りしたりくっついたりする場合があるためです。
また、長期間使わない場合は、年に1~2回ほど通気性がいい場所で干しておくのがおすすめ。着物の虫干しのタイミングとあわせて行ってもいいかもしれません。
【着付け小物】陰干しが基本
着付け小物も毎回洗う必要はありません。
腰紐、伊達締め、帯枕、帯板は脱いだ後半日ほど陰干ししておきましょう。
和装小物も着物専門クリーニングでメンテナンス可能!
「汚れがひどくてセルフではなかなか落ちない」「自分でお手入れするのは面倒」という場合は、着物専門クリーニング業者に依頼する方法も。衣替えのタイミングなどでまとめて出してみるのもよいかもしれません。
だいたい1点1,000円台~依頼できるようです。
着物や帯と同様、小物もせっかくならきれいな状態で長く使いたいもの。着付けやコーディネートだけでなく、お手入れも方法もマスターしておくことで、着物の知識も愛着も増えていくはず。
ぜひセルフメンテナンスの参考にしてみてくださいね。