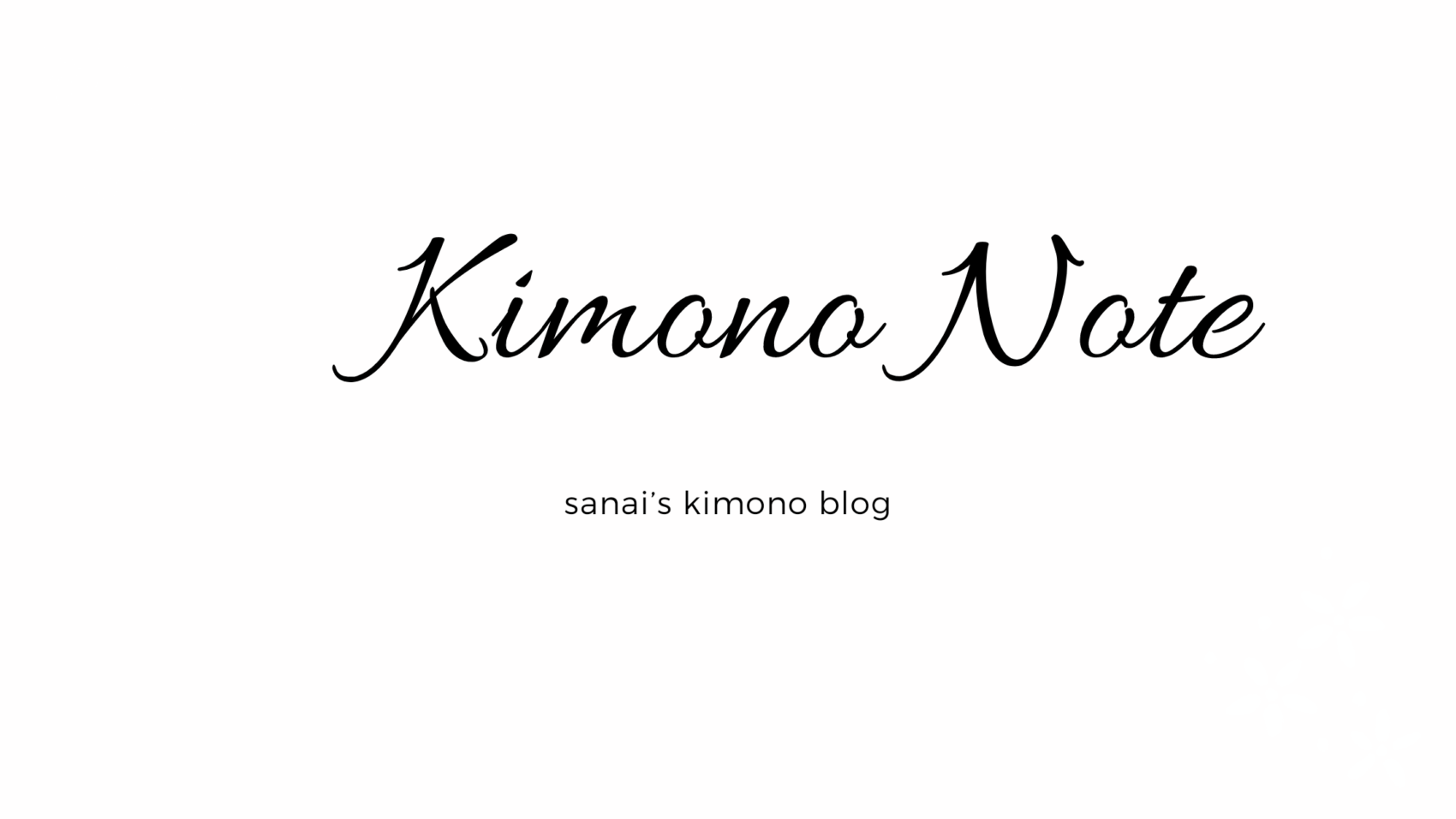「着物は洗濯機で洗えるの?」
「保管するときは防虫剤入れてもいい?」
「虫干しってした方がいいの?」
などなど、着物初心者さんを悩ませる着物や帯のお手入れや保管方法をご紹介。良い状態で長持ちさせるためにも、今一度確認しておきましょう♪
※本ページにはプロモーションが含まれています
そもそもなぜお手入れが必要なの?

洗濯などのお手入れが必要なのは、洋服も和服も同じ。けれども、和服の多くは絹でできているためとてもデリケート。絹は、湿気や水に弱いため、縮んだりカビがはえたりと、洋服に比べてトラブルが起きやすいので、念入りなお手入れが必要になります。
一方で、木綿やウール、ポリエステルなど、洋服と同じように扱える素材の着物もあります。
それぞれの素材の違いや特長については↓↓のブログでも紹介してます。

着物を脱いだ直後のお手入れ

着物を脱いだら、まず以下の2点を行いましょう。
- 着物にシミや汚れ、ほつれなどがないかチェックする
- 着物ハンガーに掛けて陰干しで一晩干す
脱いだ直後の着物は、湿気を含んでいる状態。カビや黄変を防ぐためにも、着物用のハンガーにかけて吊るしておきます。ただし、長時間干したままにしておくと、型崩れの原因になるため、一晩経ったらきちんとたたんでしまっておきましょう。帯や絹素材の襦袢も同様です。
綿やポリエステル素材の襦袢や下着は、洋服の下着のようにそのまま洗濯機で洗ってOK!着物のシミやほつれチェックは、しまう時にたたみながらするのもアリです。
また、着物にシミや汚れなどができてしまった時は、自分で無理に落とそうとせず、着物専用のクリーニングや悉皆屋に出すのがおすすめです。
着付け小物&和装小物のお手入れ方法はこちら>>
<特に汚れが付きやすいパーツ>
- 掛衿
- 袖口
- 前身頃
- 胴裏、八掛
- 裾
シーズンの終わりは丸洗いに
シーズンが終わり、長期着用しない時は、丸洗いに出しておくといいでしょう。
汚れの度合いによっては、オプションでしみ抜きを追加したり、洗い張り(着物を一旦ほどいて反物にしてから洗う洗濯方法)をしたりします。どうやってメンテナンスするかは、着物専門のクリーニング業者に相談しながら決めると安心です。

着物を自宅で洗う方法

麻・木綿・ウール・ポリエステルといった着物であれば、基本的に自宅で洗濯が可能。
手洗い、もしくは袖だたみにしてネットに入れてドライ(手洗い)コースで洗います。色移りを防ぐため着物単独での洗濯がおすすめです。
麻・木綿・ウールでもモノによっては専門業者に依頼した方がいい場合もあるので、購入時に確認しておきましょう!
洗濯洗剤は何を使う?
おしゃれ着用洗剤がおすすめ。洗浄力が高いアルカリ性の洗剤や蛍光剤・漂白剤が入っているものは、色落ちの原因になるので避けたほうがいいでしょう。
洗濯した着物の干し方は?
脱水後に長時間放置するとシワの原因になるため、よくシワを伸ばしたあと、すぐに着物ハンガーに吊るしておきましょう。直射日光は色褪せの原因になるので、風通しのいい日陰が最適。ちなみに、乾燥機は素材問わず生地の縮みが激しくなってしまうので避けた方が無難です。
必要に応じてアイロンをかける
着物がしっかり乾いたら、必要に応じてアイロンを使ってもOK。必ず当て布をして、その上からアイロンをかけます。温度設定は素材や加工によって異なるので、着物の取り扱い表示などを確認するようにしましょう。
アイロンは通常のものでもOKですが、より手軽に済ませたいときはハンディアイロンがおすすめ。
ハンガーにかけたままスチームをシュッと吹きかけてシワを伸ばせるので、着物を広げるスペースがない時や、時短で済ませたいときに重宝します。
「ツインバード」ハンディーアイロン&スチーマーを詳しく見る>>帯の洗い方は?

基本的に帯は洗濯は不要。なぜなら絹素材のものが多く、また一見洗えそうな綿や麻などの素材であっても、縮んだり型崩れたりしやすいためです。
さらに、帯には帯芯を入れて仕立てられているものが多くあります。芯の素材は様々ですが、洗濯によって芯が収縮し、帯のシワや型崩れに繋がる場合も。もし洗濯したとしても、芯まで乾かしきれずに湿気がこもり、カビの原因になることもあるので、洗わない方が無難です。
どうしても気になるシミや汚れがある場合は、着物専用のクリーニング店などに相談するようにしましょう。
着物の収納・保管方法
きちんとたたむ
着物はきちんと本だたみにして、たとう紙に入れて収納しましょう。
型崩れやシワを防ぐために、衿と裾の部分が互い違いになるようにしながら、だいたい5枚までを目安に重ねていきます。
また、刺繍や箔などがある部分には和紙や白布をあてて保管すると、変色や箔落ちを防ぐことができます。
湿気を防ぐ
保管は、防湿効果に優れ、虫を寄せ付けにくい性質を持つ桐でできた箪笥が最適。
ない場合は、プラスチックのケースなどでもOKですが、湿気が溜まらないように除湿剤を入れたり、着物専用の保存バッグを使ったりすると安心です。
防虫剤は入れていいの?
防虫剤は入れても構いませんが、複数の防虫剤を入れたり、着物に直接触れさせたりしてしまうと、変色の原因になることがあります。そのため、防虫剤は1種類のみ(できれば着物用のもの)を、引き出しの四隅に入れるようにしましょう。
また、虫対策としては、防虫効果があると言われているウコン染めの風呂敷でたとう紙を包むのもおすすめ。必ず本ウコン染めのものを使うようにしましょう。
虫干し

着物や帯は、湿気を取り除いてカビや変色などを防ぐために、年に2~3回の虫干しを行う必要があります。
おすすめの時期
以下の3回行うのが理想ですが、難しい場合は最低でも空気が乾燥している春や秋の年に2回は、点検も兼ねて行うようにしましょう。
- 土用干し(どようぼし) 7月下旬~8月上旬 / 梅雨で湿気た衣類を乾かすため。
- 虫干し(むしぼし) 9月下旬~10月中旬 / 夏についた虫を取り除くため。
- 寒干し(かんぼし) 1月下旬~2月上旬 / 衣類の湿気を抜くため。
虫干しのやり方
乾燥した空気の下で干すのが理想なので、晴天が2日以上続いた日、かつ湿気の多くなる朝と夕方は避けた10時ごろから15時ぐらいまでが最適です。一枚ずつ着物ハンガーに掛け、直射日光の当たらない風通しのよい場所で干しましょう。
室内で虫干しをする場合、室内の湿度調節が理想的にはいかないことも。そんな時には扇風機などで室内の空気を循環させて、着物が乾燥しやすい環境を作りましょう。
出典:きものtotonoe
洋服とはちょっと勝手が違う着物のお手入れ。しっかりマスターして、お気に入りの着物をキレイな状態で長く楽しみましょう♪